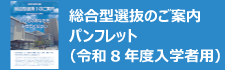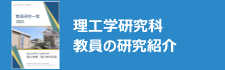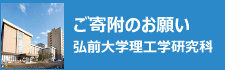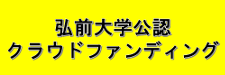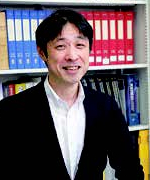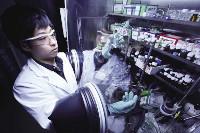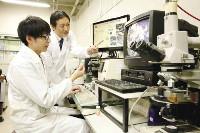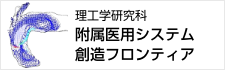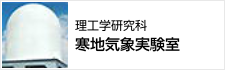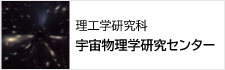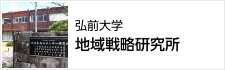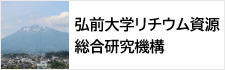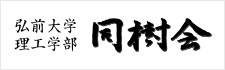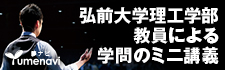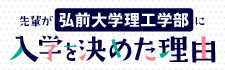- 物質創成化学科(学科Webサイト)
学びのポイント
基礎化学重視
有機化学,無機化学,分析化学および物理化学の学習に重点を置き,基礎学力を有した人材を育成します。
基礎から応用へ
基礎化学に加えて,最先端機器を用いた分析手法の習得,機能性分子および材料の開発,環境を理解し調和をはかる化学,生物の機能を模倣した材料の化学,高分子の化学について学びます。
機能性材料,環境調和型化学の推進など多彩な研究活動
人々の豊かな暮らしをつくるため,またSDGsに向けて地球環境に配慮し,限りある資源を有効利用する新しい機能性材料の創成,機能評価,微量分析等に関する最先端化学技術など,未来に向けて様々な化学研究を進めています。例えば,以下のような様々な化学分野において,世界が注目する最先端研究を行っています。
化学分野:医療材料,医薬品,半導体,触媒,プラスチック,化粧品,ゲル,ポリマー,錯体,吸着材,太陽電池,燃料電池,センサー,色素,ナノ粒子,ナノ炭素材料(CNT,グラフェン等),界面活性剤,水素製造,コロイド,分離分析,量子化学計算,脱VOC技術,脱PFAS技術,電気泳動,界面分析,生体材料, CO2有効利用,超分子構造体,撥水・撥油材料,ミセル・液晶など
取得できる資格・免許
中学校教諭一種免許状(理科)
高等学校教諭一種免許状(理科)
主な専門科目
基礎化学実験無機化学無機化学演習分析化学分析化学演習無機・分析化学実験構造物理化学構造物理化学演習反応物理化学反応物理化学演習有機化学有機化学演習有機・物理化学実験フロンティア化学錯体化学応用無機化学機器分析化学分離分析化学応用分析化学分子分光学有機合成化学有機スペクトル解析学
教職員紹介
| 氏名 | 役職 | 専門 | 研究内容 |
|---|---|---|---|
| 阿部 敏之 | 教授 | 光電気化学・光触媒 | 有機半導体・p-n 接合体・水素製造をキーワードに独自のアプローチで水の光分解系の確立をめざす |
| 伊東 俊司 | 教授 | 有機合成化学・機能分子化学 | 機能発現に向けた分子設計と合成化学的手法を駆使して機能性有機化合物の創出およびその機能開発をめざす |
| 岡﨑 雅明 | 教授 | 有機・無機合成化学 | 元素戦略に基づき普遍的な元素を用いて欠くことのできない機能性分子・材料の創製に取り組む |
| 川上 淳 | 教授 | 有機光化学 | 有機蛍光色素や蛍光性化学センサーなど光機能性有機化合物の創出と機能開発に取り組む |
| 鷺坂 将伸 | 教授 | コロイドおよび界面化学 | 有害な有機溶媒や有機フッ素化合物に頼らない将来技術に向けてCO2を有効利用したグリーン溶媒や非フッ素系低表面エネルギー材料の開発 |
| 関谷 亮 | 教授 | 無機・有機複合材料および超分子化学 | ナノグラフェンを基盤とした複合材料の開発と分子間相互作用を利用した超分子構造体の開発を推進しています |
| 竹内 大介 | 教授 | 触媒化学・重合反応 | 遷移金属錯体を触媒に用いた新重合反応を開発しユニークな構造をもつ高分子や優れた機能性高分子の創製をめざす |
| 太田 俊 | 准教授 | 錯体化学・生物無機化学 | 錯体化学の観点から,マグネシウムを基盤とする循環型エネルギー社会の構築をめざす |
| 北川 文彦 | 准教授 | 分析化学 | オンライン試料濃縮法や新規分離媒体の開発による電気泳動分離技術の高感度化・高性能化について研究 |
| 野田 香織 | 准教授 | 環境毒性学・環境化学 | 河川生態系の微量元素循環に及ぼす鉱山,ダムなどの人為影響について研究 |
| 萩原 正規 | 准教授 | 生体機能化学 | 核酸や蛋白質をナノテクノロジーのパーツとして用いた機能性材料開発やバイオ医薬品などの創製 |
| 宮本 量 | 准教授 | 量子化学 | 現代のハイテクに欠かせない希土類・遷移金属 その特異な性質の起源となるf電子・d電子を探究 |
| 山崎 祥平 | 准教授 | 理論化学 | 理論計算により分子の電子状態を探ることでミクロの観点から見た化学反応の機構解明をめざす |
| 呉羽 拓真 | 助教 | 高分子物理学・光散乱法 | 高分子材料の物性と構造を光(フォトン)をプローブとする光散乱法等により評価し,高分子材料の設計と応用に取り組む |
| 関口 龍太 | 助教 | 構造有機化学 | ユニークな分子構造をもつ新奇な有機π電子系化合物を創出し,その分子構造と物性・機能の関係を解き明かす |
| 松田 翔風 | 助教 | 電気化学 | カーボンニュートラル実現へ向けた炭素酸化物の高効率電解還元システム構築を目指す。 |