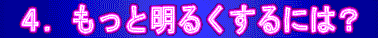
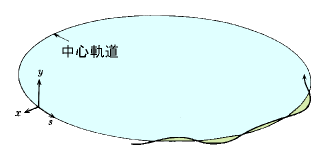 引用文献[3]より
引用文献[3]よりとなります。Kが1より小さいとき、
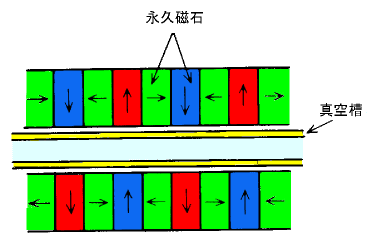
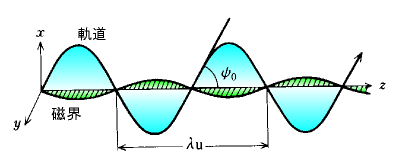
引用文献[3]より
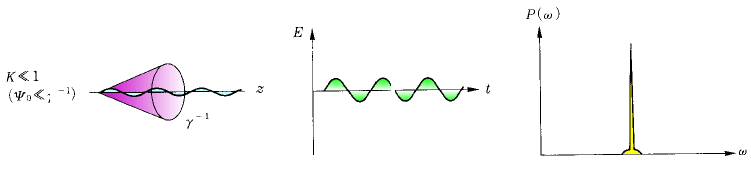
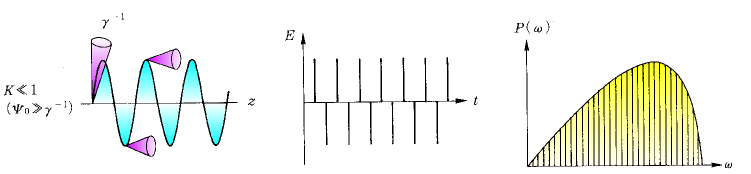
| 月刊ホームページ2002年2月号 |
| Topへ | 1.はじめに | 2.どうすれば光るの | 3.特徴は | 4.もっと明るく | 5.何ができるの | 6.日本の施設 | 7.おわりに |
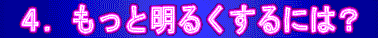 |
|
| エミッタンス | |
| 光は1点に集めるほどそこでの明るさは増します。みなさんも虫めがねで太陽の光を集めて紙に穴をあける実験を一度はやったことがあるでしょう。放射光の場合も同じです。もともと放射光は指向性の高い光なのですが、装置の仕組み上どうしても電子の軌道にふらつきが生じてしまいます。これをベータトロン振動といい、4極磁石のような中心力による収束作用をもちいたシステムでは避けられない現象です。ベータトロン振動の振幅を |
|
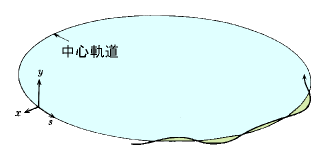 引用文献[3]より 引用文献[3]より |
|
| 挿入型光源:アンジュレータとウィグラ | |
| 上でお話しましたように、一般により明るい光やエネルギーの高い光を取り出すためには蓄積リングは高価なものになってしまいます。でも同じ仕様の蓄積リングでも、より明るい光やよりエネルギーの高い光を取り出す方法が実はあります。これまでは偏向磁石で発生した放射光をお話してきましたが、蓄積リングの図にあるように軌道の直線部分に挿入型光源を設置しここから発生する放射光を利用する方法があります。挿入型光源は図にあるように規則的に並んだ磁石によって構成されています。このような磁石の並びを軌道の直線部に設置すると、そこで電子は磁場の周期に合わせて蛇行運動をします。この蛇行運動により発生する光がアンジュレータ光やウィグラ光と呼ばれる放射光です。どのくらい大きな蛇行運動するかで放射される光の性質が異なり、アンジュレータ光とウィグラ光に分けられます。蛇行運動の大きさを示す進行方向と蛇行運動とのなす角度 となります。Kが1より小さいとき、 |
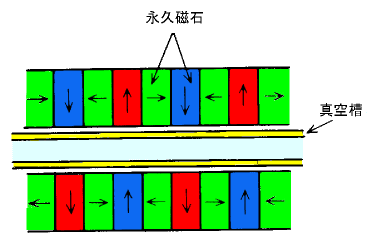 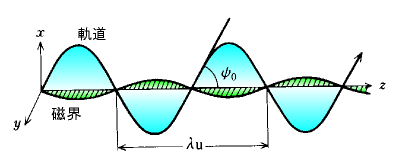 引用文献[3]より |
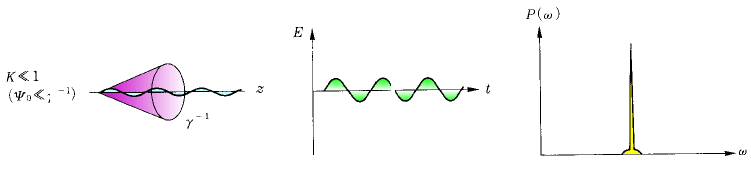
|
|
| 一方、Kが1より大きいとき、蛇行中の光は重なり合うことなく、観測者は電子が蛇行運動の山か谷にきたときのみ光を観測できます。偏向磁石との違いは電子の軌道を大きく曲げている、すなわち曲率半径が小さいことです。曲率半径が小さいと短い波長の光を出せることを前に述べました。K>1の条件により偏向磁石では得られなかった波長の短い光が出せるのです。これがウィグラ光です。前述のPFの放射光の分光特性を見てください。それぞれの光の特徴が良く分かりますね。 | |
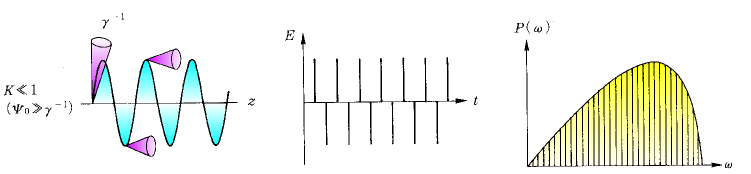
|
|
| 引用文献[4]より | |
| 3.放射光の特徴は? |
|
4.明るくするには? |

|
5.何ができるの? |
驚異の光:放射光
|
このページに関するご意見、お問い合わせは
enta@hirosaki-u.ac.jpまでお願いします。 |